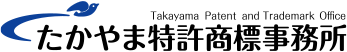ここまでのおさらいをしましょう。
指定商品「歯ブラシ(電動式は除く)」
出願したい商標
すでに見つかっている先行登録商標(先願先頭録商標といいます)
歯ブラシに、「Clean」の部分は、商品の品質や効能、用途を表すに過ぎない形容詞的文字ですので、商標審査基準の原則に従うと、「More Clean」と「モア/MORE」は、類似すると判断されるのではないかという心配が出てきた。
そこで、似たような併存登録例がないか調べたところ、
指定商品「石けん」に、
このような「モア/MORE」と「モアクリア」とが共存して登録になっていた。
しかも、出願経過を閲覧しても、「モアクリア」の方には、名義変更された形跡はなく、アサインメントバックの可能性も無いと分かった。
ということです。
でも、事案が完全に一致しているわけではないので、特許庁の審査官は、あっさりと、「事案が異なる」として、このような併存登録例があったとしても、「More Clean」と「モア/MORE」とが類似していると判断する可能性は十分に考えられるということでした。
そこで、最終兵器の登場です。
「モア/MORE」が、もし、3年以上使用されていないのであれば、「不使用取消審判」という審判を請求して、「モア/MORE」の商標登録を取り消すことができます。
もし、「モア/MORE」の商標登録を取り消したら、「More Clean」の拒絶の根拠になる先願先登録商標である「モア/MORE」の商標権が消滅することになりますので、「More Clean」の商標権を獲得することができます。
実際、この事案では、不使用取消審判を「モア/MORE」に対して請求し、無事に、「More Clean」の登録を勝ち取ることができました。
不使用取消審判は、最終兵器になりますが、意外と、簡単な手続きです。なぜなら、商標法第50条第2項によって、登録商標を使用しているということを証明する義務は、商標権者の方にゆだねられているからです。難しい法律用語でいうと、「挙証責任の転換」というのですが、この条文があるからこそ、不使用取消審判は、お気軽な審判なのです。
実際、審判請求書は、2~3枚程度で定型的な文章で提出するだけです。ただし、注意が必要なのは、どの指定商品を取り消すと請求するかです。取り消す対象の指定商品を間違うと、いけません。拒絶理由が解消しませんから。
このケースはシンプルなので、楽なのですが、もっと、複雑に指定商品が入り組んでいると、大変です。しかも、対象となる商標権が複数あれば、どの商標権を取り消すかを漏れることなく選ばなければなりません。
審判請求書自体の記載は簡単ですが、そのバックにある調査がかなり慎重で大変ですね。その調査だけで、過去のややこしいケースでは、1日くらいかかってしまうときもありました。
さて、審判請求して、相手方が、使用事実を証明できない場合は、たいてい、そのまま、相手方は、無視して応答しません。
すると、特許庁で、取消の審決がなされます。
これで、無事に、拒絶理由が解消して、登録に導くことができます。
なお、注意が必要ですが、取り消された方の商標権者は、不使用取消審判に要した費用を負担しなければなりません。審判に負けて、なんら応答していない場合でも、たいてい、印紙代の支配義務が発生します。この手続きは、実は、何十年も弁理士業界内で無視されてきた手続きなのですが、また、詳しく、このブログで、ご紹介します。
以上、何回かに渡って、どのような思考回路で不使用取消審判まで、持ち込むかをご紹介しましたが、これで全部ではなくて、本当に不使用なのかどうなのかをネットや興信所等を使って調べたり、不使用取消審判を請求しなくても登録になる論理がないか考えたり、他の併存登録例や審決例を調べたりと、なかなかお客様からは見えないところで、いろいろ調査検討します。
このケースは、実は、過去に、他の特許事務所に依頼して拒絶査定になったあと、再度、登録を目指して、私のところに依頼が来たということ経緯がございます。
弁理士を目指す方や弁理士になりたての方、また、弁理士として長くしている方でも、あらゆる可能性を考慮して、最善の努力を取るということや、あらゆるリスクを想定して何が必要なのかを考慮するという視点をもってもらいたいです。
そもそも、商標法4条1項11号で拒絶査定になるということは、裏返せば、商標権侵害として訴えられる可能性があるということなのです。
「あー意見書の反論が認められませんでしたね」では済まないと思いますよ。その製品が特に、実施されているものであればなおさらです。
まあ、依頼者が、「そんなん別に構いませんわ、なんとかなるんちゃいます」といわれるのであれば、それも1つの答えです。
実際、私も、そういう視線で物事を考える場合もよくありますから。
なかなか難しいことかも分かりませんが、依頼者の状況や個人的な性格、社内のコンセンサス、担当者の立場など、あらゆるバックボーンや精神状態、心理状態、同業者の雰囲気などを加味した上で、できること、できないこと、やるべきこと、やらなくていいこと、それらをアドバイスできるように心がけています。