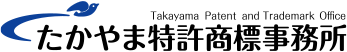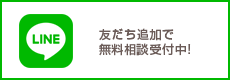AIとともに歩んだ明細書作成、この1年。
AIを明細書作成に本格導入してから、気づけば1年が過ぎました。
いまでは、AIと議論しながら構成を組み立てることが、すっかり日常の一部になっています。
「AIで書く」から「AIと考える」へ
導入当初は、AIに文案を出させて整える——そんな使い方でした。
ところが今では、AIが構造を把握して論理を整理し、こちらが技術思想を検証するという、まるで共同起案のようなスタイルが自然になりました。
特許明細書の作成は、単なる文章作業ではなく、技術の構造を言語化する知的設計行為です。
AIはそのプロセスを加速させ、論理の整合性を保ちながら、思考を可視化するツールになっています。
図面を「読む」AIとの共進化
この1年で最も大きな変化は、AIに機械図面を理解させるための指示技術(プロンプト技法)が飛躍的に洗練されたことです。
図面の構成要素、符号、作動経路、動きの意味を段階的に教え込むことで、AIが図面と文書を連動して考えるようになりました。
この結果、図面と文章の整合チェックや、段階的な構造説明が驚くほどスムーズになり、従来の作業フローそのものが変わりつつあります。
「速さ」ではなく「精度」と「一貫性」
AI導入の目的は単なるスピードアップではありません。
重要なのは、構成・請求項・図面・効果の整合を保ちながら、ぶれない論理を維持すること。
この1年の実務で、AIは“速度のための道具”ではなく、“精度を支える相棒”になりました。
これからの実務
AIが当たり前に使われる時代に入った今、特許実務に求められるのは「AIを使える」ことではなく、AIに何を考えさせ、どこまで任せ、どこで人が判断するかを見極める力です。
この1年間で得た知見は、今後さらに発展し、明細書作成・図面解析・構成検証の新しい標準へと進化していくと感じています。
おわりに
AIと共に考え、整理し、構築する知財実務は、すでに特別なものではありません。
それが日常となり、次の基盤となる。そんな時代に立っていることを実感しています。
これからも、AIとともに進化する実務の現場から、気づきや工夫を発信していきます。