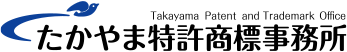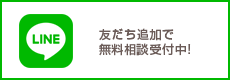–「技術」と「法」の正しい理解に基づく、前向きなAI活用のために–
2025年3月28日策定
弁理士 高山嘉成
※このガイドラインは、第一版であり、予告なく変更されます。
第1条 本ガイドラインの目的
本ガイドラインは、当事務所におけるChatGPT(OpenAI)等の生成AIを、安全かつ効果的に利活用するための基本的指針を定めるものである。
当ガイドラインは、弁理士会が発行した「AI利活用ガイドライン(β版)」が、生成AIの本質的理解や技術的実態の分析を欠いた形式的な内容にとどまっていることを問題視し、実務と技術の両面から現実的かつ積極的なAI利活用を推進する立場に立って策定する。
第2条 利用対象と方針
- 当事務所では、OpenAIが提供するChatGPTのWeb版(ChatGPT PlusまたはPro)を利用する。APIは使用しない。
- ただし、利用にあたっては常に「カスタム設定」にて「すべての人のためにモデルを改善する」をオフに設定(オプトアウト)し、再学習に使用されない状態を維持する。
- クライアントの発明内容、技術情報、契約文案等をChatGPTに入力する場合、以下の条件をすべて満たす限り、新規性喪失および守秘義務違反には該当しないと判断する:
- ChatGPTの入力情報が外部に開示されないこと
- オプトアウト設定により、再学習対象外であること
- クラウド上の一時的な保存が、技術的理由に基づくものであり、公開とは評価されないこと
第3条 生成物の取り扱いと責任
- ChatGPTから出力された文章や提案について、著作権その他の権利は当事務所(ユーザー)に帰属する。
- 出力内容が他者の知的財産権(特に特許・著作権)に抵触する可能性がある場合、弁理士としての専門的見地から検討を加えた上で利用判断を行う。
- ChatGPTが生成した結果をそのままクライアントに提供することは行わず、常に弁理士が内容を確認または編集し、最終判断を行う。
第4条 クライアントへの説明義務と信頼構築
- 当事務所は、生成AIの利用に際して、クライアントに対し以下の説明責任を果たす:
- どのような技術的仕組みでChatGPTが動作しているか
- 入力データの再学習や外部漏洩の有無(リスクと対策)
- 生成された文書の著作権、法的責任、利用可能性
- 「クライアントの同意があれば使ってよい」とする形式的な姿勢ではなく、弁理士として技術と法の正確な理解に基づく助言を行うことを基本とする。
第5条 ガイドラインの見直しとアップデート
生成AI技術は急速に進化しており、OpenAIの仕様・利用規約・社会的認識も随時変化する可能性がある。
当ガイドラインは、技術動向・実務ニーズ・法的評価に応じて柔軟に見直すものとし、常に「最も合理的かつ実務的な判断基準」で運用を行う。
【付記】弁理士会のガイドライン(β版)についての見解
弁理士会によるAI利活用ガイドライン(β版)は、生成AI技術の実態やクラウド運用の一般的特性を正しく理解しているとは言い難く、
- 「サーバにデータが保存されるから危険」
- 「再学習されるか否かの技術設定を無視して同意の有無で判断する」
といった、本質を外した形式論に基づく過剰な萎縮を助長する内容が含まれている。
当事務所は、こうした思考停止的なリスク回避型アプローチに与せず、弁理士こそがAI技術を正しく理解し、リスクを制御しながら積極的に活用する先導者であるべきと考えている。