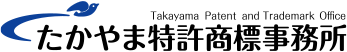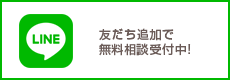〜特許や秘密情報は大丈夫?弁理士が解説する“正しい使い方”〜
たかやま特許商標事務所
弁理士 高山嘉成
「ChatGPTにアイデアを入力したら、外に漏れてしまって特許が取れなくなるのでは?」
最近、このような不安を感じている方が増えています。
弁理士会からも「AI利活用ガイドライン(β版)」が出されましたが、「クライアントから同意を得れば使ってもよい」という消極的な姿勢にとどまっており、本来弁理士が果たすべき説明責任や技術理解の視点が十分とは言えません。
そこで今回は、ChatGPTを安心して使うために、弁理士としてどこに注目すべきか、利用規約などの内容をもとにわかりやすくご紹介します。
✅ 1. 「入力した情報」がChatGPTに再学習されるか?
ChatGPT(Web版)では、初期状態ではユーザーの入力が将来のAIの学習に使われる設定になっています。つまり、あなたが入力した内容が、次のバージョンのChatGPTの訓練材料になる可能性があるということです。
ただし、これは設定で変更できます。
「設定」→「データコントロール」→「全ての人のためにモデルを改善する」をオフにすれば、再学習には使われません。これをオプトアウト設定といいます。
また、ChatGPT API経由(たとえばAzure OpenAIなど)での利用では、デフォルトで再学習には使われない設計になっています。
👉 発明の内容などの機密情報を入力する場合は、オプトアウト設定をするか、API型を使うことが基本です。
✅ 2. 入力内容が「外部に漏れる」ことはあるのか?
OpenAIのプライバシーポリシーでは、ユーザーが入力した内容の第三者への開示について、限定的な場合だけに限った開示となっています。これは他のクラウドサービス(GmailやDropboxなど)でも同様です。
👉 サーバに一時保存されるからといって、それだけで「情報が公開された」「新規性が失われた」とはなりません。
第三者が知り得ない状態にある限り、新規性喪失には該当しません。
✅ 3. ChatGPTが生成した文章の著作権は誰のものか?
OpenAIの利用規約では、ChatGPTが出力したコンテンツについて、著作権を含むあらゆる権利は「ユーザーに帰属する」と明記されています(商用利用も可能です)。
つまり、ChatGPTに文章を作らせても、その成果物を自分のものとして自由に利用してよいということです。
👉 ただし、自分で作ったように見えても、その内容が他人の著作物や特許に抵触していないかのチェックは必要です。AIはそこまで判断してくれません。
✅ 4. ChatGPTの出力内容が他人の権利を侵害することはあるか?
ChatGPTは、学習データからパターンを見つけて新しい文章を生成するツールです。
そのため、意図せず他社の特許に似た内容を出力したり、既存の文章と酷似した内容を生成する可能性はゼロではありません。
特許や著作権の観点からは、次のような注意が必要です:
- 特許アイデアの検討には、クリアランス調査(他社特許の確認)を行うこと
- 文章や画像の商用利用では、出力内容が他者の著作物と酷似していないか確認すること
👉 ChatGPTは便利な道具ですが、生成物をそのまま使う場合は、最終的な判断と責任は利用者にあることを忘れてはいけません。
✅ 5. 弁理士として注目すべきその他のポイント
- 利用規約は頻繁に更新される
ChatGPTは急速に進化しており、利用条件も数ヶ月ごとに見直されます。定期的なチェックが必要です。 - クライアントの同意だけでは不十分
ガイドライン(β版)は「同意があれば入力してよい」と述べていますが、そもそもどの設定・環境ならリスクが回避できるかを、弁理士自身が説明できることが重要です。
■ おわりに:弁理士がAIを“正しく使う”時代へ
ChatGPTは、発明のアイデア整理、文章の草稿、特許業務の効率化において、大きな力を発揮するツールです。
だからこそ、弁理士こそがその仕組みとリスクを正確に理解し、「こうすれば安全に使えますよ」とクライアントに指導できる存在であるべきだと考えています。
「ChatGPTは危ないから使わない」ではなく、
「ChatGPTはこうすれば安全に使える」と言える弁理士が、これからの知財実務をリードしていく。
そのような未来を目指し、今後も正確な情報発信と実践を続けていきたいと思います。